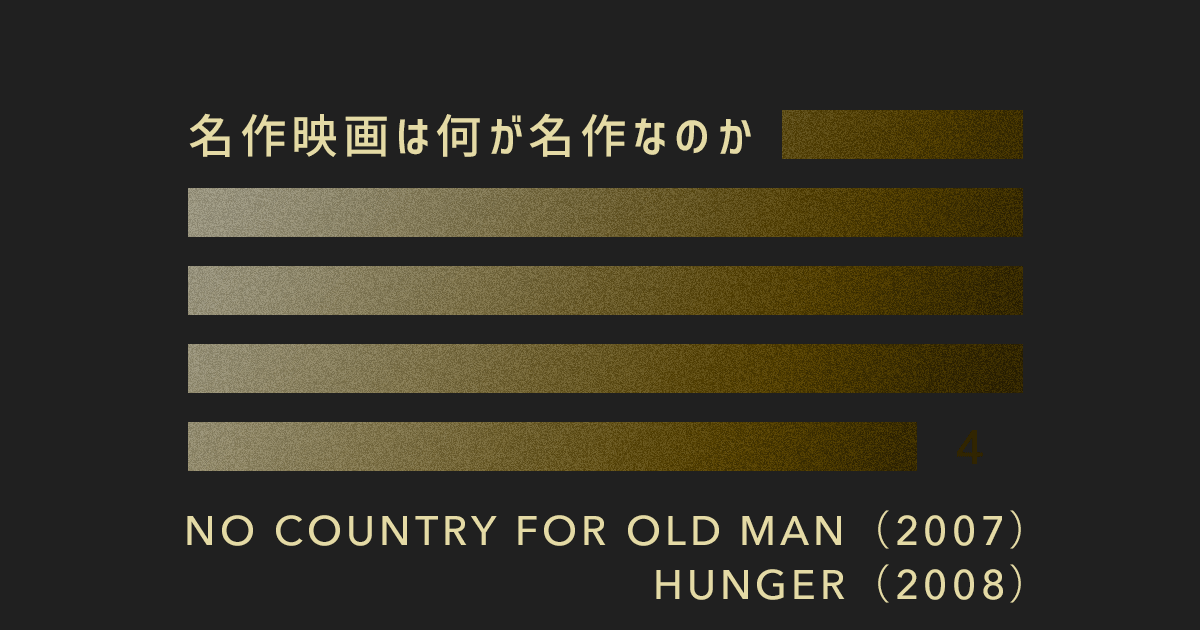シンプル・イズ・ベストの演出術『ノー・カントリー』『HUNGER/ハンガー 静かなる抵抗』 ─『名作映画は何が名作なのか』その4

技術をあえて制限する映画たち
この連載「名作映画は何が名作なのか」では名作映画がいかに技巧的に、内容的に工夫がこらされているのかを解説しています。ただし、私も勘違いしそうになることは多いのですが「技術的に優れた映画」と「面白い映画」は必ずしも一致しません。決して「技術よりも心が大事」と言いたいわけではなく、高度で複雑な技術をはりめぐらせなくても人の心をつかむ映画はできるのではないでしょうか。
たとえば、現在のハリウッド映画を見ていると「技術」は確かに進歩しています。ドローンやクレーンを駆使して撮影が行われ、めまぐるしい量のカットが割られ、CGで画面を補整して派手なアクションシーンが完成します。しかし、だからといって、『駅馬車』(1939)のように、戦前の西部劇がワンカットで表現していた早撃ち描写以上の緊迫感があるわけではありません。いわば、現在の映画は技術が飽和している状態です。予算が潤沢な作品になると、あまりにも技術の選択肢が多いので、つめこみすぎて散漫な印象を残すのです。もちろん、多彩な技術を使いこなしてしっかりと自分の映画を作り上げていた監督もいます。それでも、まずは作品ありきが基本であり、技術から逆算して映画を作るのは本末転倒に思えます。
そこで、現代映画ではあえて「技術を制限する」手法で、映画の根源に触れようとするケースもあります。今回解説する2本の映画と2人の映画作家は、100年近く前の映画作品とほとんど変わらない技術を用いながら、全く「古臭さ」を感じさせません。シンプル・イズ・ベストとでもいうべき演出術に迫っていきましょう。
コーエン兄弟の確信犯的な単調さ
兄ジョエルと弟イーサンのコーエン兄弟は、アカデミー賞やカンヌ国際映画祭をはじめ数々の映画賞を獲得してきたベテラン映画監督です。自主制作のデビュー作『ブラッド・シンプル』(1984)で注目されてから、長年、批評家とコアな映画ファンから支持されてきたのですが、『ファーゴ』(1996)以降はヒットにも恵まれるようになりました。クエンティン・タランティーノやロバート・ロドリゲスのような、自主映画からメジャーにステップアップした監督たちのロールモデルといえるでしょう。
しかし、私はコーエン兄弟が「超絶技巧」を武器にしている映画監督だとは思っていません。彼らの映画にはまぎれもない個性があります。予想もつかないストーリーテリングとブラックユーモア、人物造形の妙など、「コーエン兄弟的」と呼べるテクニックはいくつも見られます。しかし、画面だけに限れば、コーエン兄弟の映画はどちらかというと単調です。これは、彼らが自ら脚本を書き、物語を丁寧に見せることにこだわっているからでしょう。『バートン・フィンク』(1991)や『ファーゴ』、『ビッグ・リボウスキ』(1998)など、複雑なプロットをさりげないユーモアでトッピングした作品では、単調な画面が吉と出ます。テンポをつかみやすいので、観客はストーリーを見失うことなく鑑賞できるからです。
コーマック・マッカシーの小説『血と暴力の国』を映画化し、アカデミー賞作品賞と監督賞を獲得した『ノー・カントリー』(2007)は「コーエン兄弟の最良の部分」が発揮された作品でした。全編が名シーンの連続ですが、特に不気味な殺し屋、アントン・シガー(ハビエル・バルデム)が賞金稼ぎのカーソン・ウェルズ(ウディ・ハレルソン)と対面するシーンをピックアップしたいと思います。
ホテルの一室、シガーが空気銃をウェルズに向けたまま椅子に腰を下ろします。シガーの全身が映っていますが、このカットは後で効いてきます。ウェルズも神妙な面持ちで正面に座っています。基本的にはウェルズが命乞いをし、シガーが受け流すやりとりを、2人のバストショットを交互に映していくだけで表現する単調なカット割です。それでも観客はシガーの恐怖に震え、いつ銃が撃たれるのだろうとドキドキします。カット割が淡々としているからこそ、発砲のタイミングが全く読めないのです。本作でアカデミー主演男優賞を受賞したバルデムの怪演と、ハレルソンの恐怖の芝居も秀逸です。
会話が途切れたところで電話が鳴り響きました。すると、再びシガーの全身のカットに戻ります。画面左に黒電話があり、観客の意識は自然とそちらに向くはずです。思わずシガーの銃口から注意が反れたタイミングで、彼は引き金を引きます。これ以上ないくらい、驚かされるタイミングとしかいいようがありません。シガーが腰掛ける瞬間から、発砲までを逆算して構成されている見事なシークエンスです。
このシーンをより特別にしているのは、電話が鳴った直後、シガーが微笑みながら首を傾げるカットです。このとき、シガーの動きに合わせて、ほんの少しだけカメラがパン(水平移動)しています。コーエン兄弟の演出をさんざん「単調」と評してきましたが、単調だからこそ些細な変化が画面のアクセントになりえます。奇をてらいすぎた演出は、逆に観客を変化に対して鈍感にするでしょう。『ノー・カントリー』のような緊張感が命の映画では、「普通さ」こそがもっとも恐ろしく見えるのです。
ワンカットで演技合戦を盛り上げる
コーエン兄弟と同じく、『それでも夜は明ける』(2013)でアカデミー作品賞と監督賞を受賞したスティーヴ・マックイーン監督も画面が特徴的です。彼の映画ではワンカットでの長回し、あるいは俯瞰的なアングルからのマスターショット(編集の核となるショット)が印象的に登場します。『それでも夜は明ける』の目を背けたくなるような奴隷への鞭打ちや、首に縄をかけられる虐待のシーンが象徴的でしょう。
たとえば、ジム・ジャームッシュ監督もよく自作で長回しを登場させます。しかし、ジャームッシュが日常の「何気なさ」を表現するためにあえて単調な固定ショットで長回しを行うのに対し、マックイーンの意図は逆です。観客が現実から目を背けられないよう、集中を強いるように長回しを用いるのです。よって、マックイーン監督作で長回しが出てくると、作品の核心となる場面だと考えられます。
処女作には監督の原点が見えるといいますが、マックイーンの場合も例に漏れません。1981年、北アイルランド紛争の活動家の壮絶な抗議活動を描いた処女長編『HUNGER/ハンガー 静かなる抵抗』(2008)にも長回しシーンが出てきます。物語がクライマックスに向かうための重要な会話をマックイーンはワンカットで撮影しました。
舞台は刑務所内の設問室です。画面左側には上半身裸のIRA闘士、ボビー・サンズ(マイケル・ファスベンダー)が座っています。右側に腰掛けるのはモーラン神父(リアム・カニンガム)です。サンズが服を着ていないのは、囚人服を押しつけられたことに対する抗議です。刑務所には「政治犯は私服のまま収容される」という決まりがありましたが、イギリス政府はIRAを政治犯とは認めず、私服を許可しませんでした。
対面したサンズとモーラン神父を、固定したミドルショットが映し出します。驚くことに、これから20分近くもカメラは微動だにしません。2人は逆光になっており、表情もほとんど読み取れないままです。
どうしてこんな演出を行っているのかというと、ここが本作で唯一の会話シーンだからです。本作はほとんど台詞らしい台詞がなく、表情と悲鳴だけで囚人たちの苦悩を表現しています。そのため、はっきりとサンズが自分の心情を口にする場面は観客の集中を促すように撮りたかったのでしょう。事実、サンズたちの表情が見えないことで、観客はより会話の内容に注意を払おうと意識させられます。
サンズは囚人たちのリーダー格として、これまで裸で過ごしたり、糞尿で監房を覆ったりするなどのデモを扇動してきました。しかし、全ての抗議はイギリス政府を動かせず、サンズはついにハンガーストライキ(ハンスト、要求が通るまで一切の食べ物を口にしない抗議活動)を決意します。
既にサンズに賛同する75人の囚人がハンストを志願しています。サンズはまず、自分が先陣を切ってハンストを行い、餓死したら次の囚人がハンストを始める予定です。モーラン神父は聖職者として、同胞としてサンズを食い止めなければいけません。2人の信念がぶつかり合います。
画面の構図が変わらないからこそ、2人のちょっとした語気の変化や、タバコを吸う仕草などが効いてきます。演技派同士の言葉の応酬は演劇にも似ていますが、演劇ならば「画面を区切って観客の目を釘付けにする」演出は不可能です。シンプルであるがゆえに、映画ならではの条件を活かせたシーンだといえるでしょう。
ワンカットの間、2度の沈黙が訪れます。1度目はサンズが「3月からハンストを決行する」と口に出した後、2度目は神父に「(自信がなかったからこそ)私に話したかったのだろう」と看破された直後です。いずれも、間を持たせるためにサンズがタバコに手を伸ばします。また、沈黙の直後に芝居のトーンが変わり、画面のムードを移行させていくのは、まさしく名演です。長回しは俳優に確かな実力がなければ成功しない手法です。その後、ファスベンダーはマックイーン監督作に出演し続け、いずれも高い評価を得ていますが、俳優と監督の信頼関係は『HUNGER』の時点ではっきりと認められます。
新鮮な食材は、シンプルに調理した方が本来の味を引き立てるように、素晴らしい被写体に恵まれた現場では複雑な演出が不要なこともあります。「シンプル・イズ・ベスト」を心がけられる映画は、幸福なキャストとスタッフに恵まれた証かもしれません。